沖縄タイムスに驚きの記事が掲載されていました。「赤いスズメ」と「トリ食うクモ」。
心優しい方、過激シーンの苦手な方、心臓の弱い方は【閲覧注意】!!これから先は見ないで下さい。(I)※記事中の氏名は匿名としています。(特に理由はありませんが…??)
第1弾:「目の錯覚か…」“赤いスズメ”発見 沖縄の同じ島で“赤いカモ”も確認(沖縄タイムス2022年5月4日)
沖縄県の多良間島で「赤いオナガガモ」と「赤いスズメ」が発見され、話題になっている。専門家は「黒色が薄くなるなどの発色異常が原因ではないか」と分析している。多良間村塩川の農業、Hさん(74)が4月11日に「赤いオナガガモ」、15日に「赤いスズメ」を撮影した。
オナガガモの全長は雄で75センチ、雌で55センチほどと大型で、体と首が細長い。県内には冬鳥として飛来する。「赤いオナガガモ」は雌とみられ、本来なら全体が褐色で黒褐色のまだら模様だが、全体が赤っぽい。Hさんは「全国でちらほら見られているらしいが、多良間では初めて見た」。写真(多良間島で確認された「赤いオナガガモ」)
「赤いスズメ」は塩川の村議、Kさん(59)と妻のYさん(49)が4月初旬に見つけ、「目の錯覚ではないか」「赤い土がついただけではないか」と普通のスズメと何度も見比べていたという。
Kさんは「雨にぬれても色落ちしないのでびっくりしている」、Yさんは「赤は縁起がいいと聞く。多良間でもいいことがあったらうれしい」と喜んでいる。写真(普通の色のスズメと一緒に餌を探す「赤いスズメ」~多良間村塩川の牧場&石垣島で観察された「赤いスズメ2羽」と普通のスズメ)
写真を見た山階鳥類研究所のM研究員は「『赤』とも表現できるが、赤色は幅が広く、鮮明な赤から赤茶までさまざま。このスズメは、赤茶色」と指摘。「黒色部が本来の真っ黒ではなく薄く、黒のメラニン発色の異常と同時に茶のメラニンの発現と発色が本来とは変化した異常な発色をしていると考えられる」と原因を分析した。(編集委員・F)
第2弾:【閲覧注意】「信じられない」
クモが鳥を食った(沖縄タイムス2011年8月30日)
糸満市米須の駐車場そばの森林で、体長約15センチのオオジョロウグモがシジュウカラを食べているところを、パイロットのEさん(60)がカメラに収めた。今月10日午前10時ごろから翌11日午前9時ごろまで、断続的に撮影した。生物学が専門のゲッチョ先生ことM沖縄大学准教授は「珍しい。クモが鳥を食べるらしいと聞いたことはあったが、写真では初めて見た」と驚いた。
写真①シジュウカラを食べ始めたとみられるオオジョロウグモ=10日午前、糸満市米須→⑤翌11日午前9時ごろ
オオジョロウグモは、セミやチョウを食べるが、クモの仲間では糸が強く、鳥を食べることもある。食道の小さいクモは、巣にかかった鳥に毒を入れて動けなくさせ、時間をかけて汁にして飲み込むという。
Eさんによると、クモは翌11日の午前9時まで食べ続け、最後は羽毛だけが残ったという。20年以上、昆虫など自然の生き物を撮り続けているが「鳥がクモを食べるのなら分かるけど、初めは誰かのいたずらじゃないかと思った。人間がする訳もないし…。今でも信じられない」。
※オオジョロウグモ
は東南アジア、東アジア、オセアニアに分布するジョロウグモの仲間です。国内では奄美大島以南に生息し、日本に生息するクモの中で最大の種です。メスの体長は3.5
– 5cmほどになり、脚も含めると20cmほどになるものもいます。巣も1 –
1.5mほどの大型のものを作ります。一方で、オスの体長は0.7 –
1.0cmほどです。本州のジョロウグモが人家近くでも普通にみられるように、オオジョロウグモも森林だけではなく、公園や神社といった人為活動がある場所で普通にみられます。(いきものコレクションアプリBiome(バイオーム)より)
写真①オオジョロウグモ ➁オオジョロウグモのオス ③オオジョロウグモのメス
(中央)とオス (左上)
※シジュウカラは全長14.5cm。体重は14gくらいです。日本ではほぼ全国に分布していますが、北日本に多く、西日本には少ないようです。平地から山地の林にすみますが、市街地、住宅地で見ることも多い鳥です。木の穴に巣をつくりますが、人工的な狭い穴にもよくつくります。「ツツピン
ツツピン」と鳴いて、鳥の中でもいち早く春を告げるシジュウカラは、市街地でもおなじみの鳥です。四十の雀と書いてシジュウカラ。たくさん群れるから、という説や、スズメ40羽分の価値があったことから名付けられたという説もあります。写真④シジュウカラ
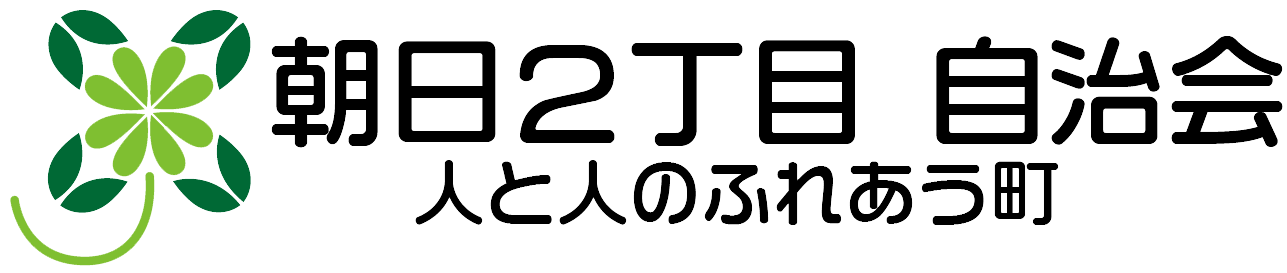










=2月23日(小林雅裕さん撮影)(沖縄タイムス)-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)